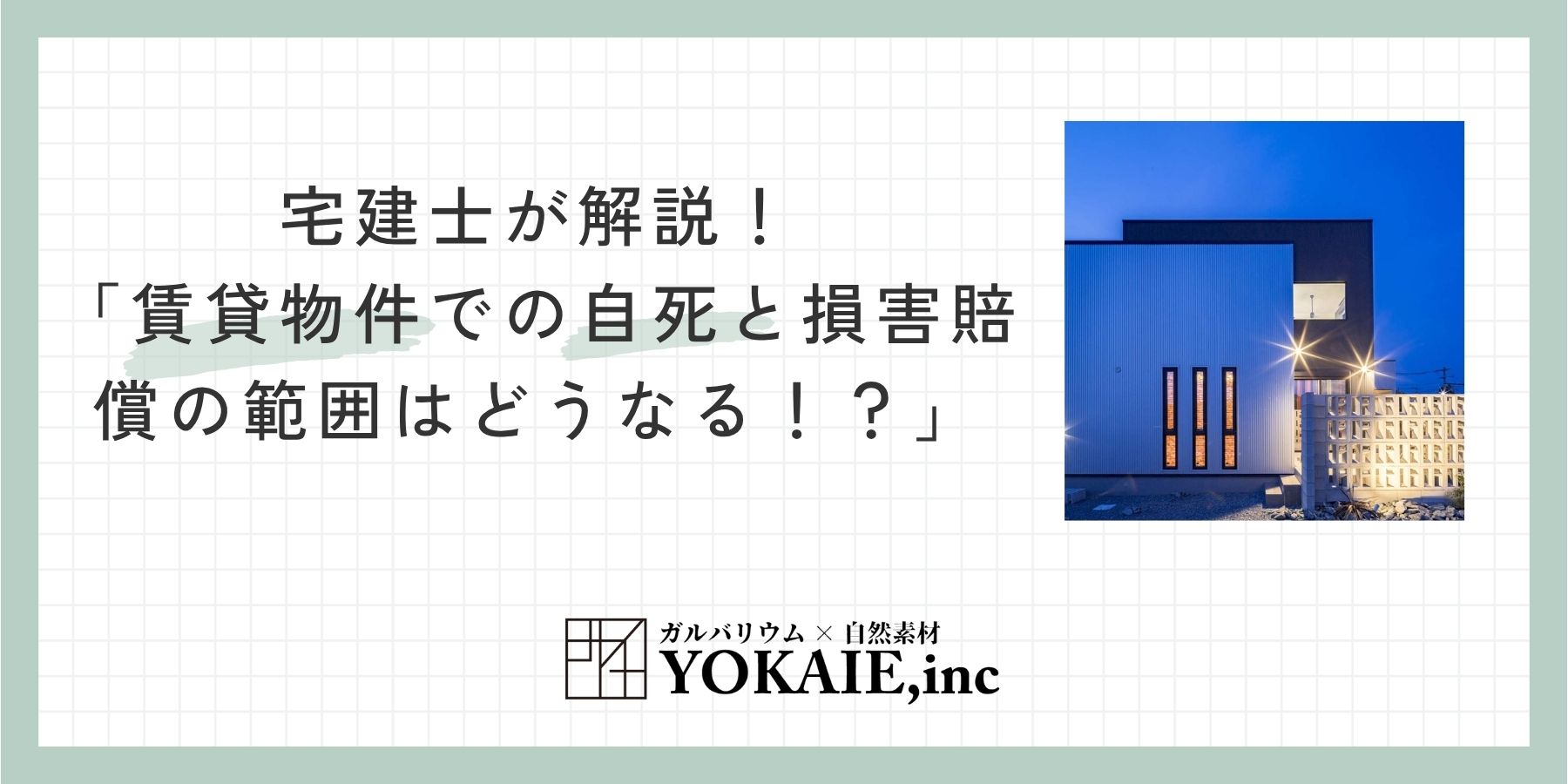

今回は非常にデリケートな「賃貸物件での自死」のお話。万が一のことは常に考えておかなければなりません・・・。
賃貸物件での自死と損害賠償の範囲はどうなる!?
身内が賃貸アパートやマンションで自死という事態になった場合。
そんなこと、考えたくもないですが…。残された家族はどのように立ち振る舞えばいいでしょうか。被相続人となる方々にも、責任がかぶさってくるのでしょうか。
今回は、非常にデリケートなテーマではありますが、万が一の際に冷静に対処できるよう、賃貸物件での自死にまつわる損害賠償と告知義務について、工務店所属の宅建士という視点から、詳しく解説します。

1. 自死は「善管注意義務違反」にあたる
まず大前提として、賃貸借契約において、入居者様は「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」を負っています。これは、借りたものを適切に管理し、社会通念上、その価値を不当に損なうようなことをしないという義務です。
民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
過去の裁判例では、入居者が室内で自死することは、この善管注意義務に違反する行為と判断される傾向にあります。なぜなら、自死は物件に「心理的瑕疵(かし)」を生じさせ、その経済的価値を著しく低下させるからです。
したがって、賃貸人(オーナー)は、亡くなられた入居者様の相続人(ご遺族)や連帯保証人に対し、損害賠償を請求できる可能性があります。

2. 損害賠償の範囲:何が請求できるのか?
では、具体的にどのような費用を請求できるのでしょうか。主な損害賠償の項目は以下の通りです。
(1)原状回復費用
自死の状況によっては、特殊な清掃や大規模なリフォームが必要になる場合があります。
- 特殊清掃費用
通常のハウスクリーニングでは落とせない、臭気や汚損がある場合に必要となります。専門業者による消臭・除菌・消毒作業の費用です。- リフォーム・修繕費用
壁や床の張替え、建具の交換など、自死に直接起因して汚損した箇所の修繕費用がこれにあたります。
これらの費用は、入居者様の契約違反によって生じた損害として認められます。
民法621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(2)逸失利益(家賃収入の減少分)
自死があった部屋は「事故物件」となり、次の入居者を見つけるのが困難になったり、家賃を下げざるを得なくなったりします。この家賃収入の減少分も、損害として認められる可能性があります。裁判例によれは、賃料1~3年間分の賃料相当分が認定されることが多いようです。
裁判例の傾向として、以下のような判断がされることが多いようです。
- 賃貸不能期間の家賃
事故後の一定期間(約1年間)は、次の入居者が決まるまでの「賃貸不能期間」として、家賃全額の損害が認められる場合があります。- 賃料減額期間の家賃
その後の期間(約2年間)は、事故があったことを告知するため、家賃を半額程度に下げて募集せざるを得ないとして、減額分の損害が認められることがあります。
ただし、これらの期間や金額は、物件の立地、広さ、入居者の需要などによって個別に判断されるため、一律ではありません。
(3)未払い賃料
入居者様が亡くなられた時点で未払いとなっている家賃があれば、その分も相続人や連帯保証人に請求できます。これは、賃貸借契約上の義務として当然の請求です。
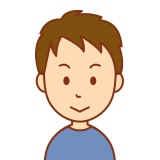
その他、不動産価値の評価減についてが考えられますが、原則として損害賠償の範囲に含まれないと考えられます。
3. 請求の相手は誰になる?
自死された入居者様ご本人に請求することはできませんので、主に以下の2者に請求することになります。
- 相続人(ご遺族)
賃貸契約の名義人(被相続人)が亡くなると、賃貸借契約上の権利や義務は相続人に引き継がれます。しかし、相続人が「相続放棄」をした場合、その相続人は賠償義務を負いません。相続放棄は、亡くなられてから3ヶ月以内に家庭裁判所への手続きが必要です。- 連帯保証人
連帯保証人は、賃貸契約の名義人(被相続人)が負う債務を保証する義務があります。そのため、相続人が相続放棄をした場合でも、連帯保証人は賠償責任を免れません。2020年4月の民法改正により、個人保証契約には「極度額(保証の上限額)」の設定が義務付けられていますので、この極度額の範囲内で賠償責任を負うこととなります。(2020年4月以降に合意された保証契約に「極度額」の設定がない場合、無効となります。)
4. 告知義務の範囲と期間
自死があった物件は「心理的瑕疵物件」として、次の入居者様へ告知する義務が生じます。
- 告知が必要なケース
自死、他殺、火災による死亡など、一般的に「嫌悪されるべき事由」に該当する死因の場合です。- 告知が不要なケース
老衰や病気による自然死、日常生活での不慮の事故(階段からの転落、入浴中の溺死など)の場合は、原則として告知義務はありません。※ただし、死後長期間放置されて特殊清掃が必要になった場合は、告知義務が生じる可能性があります。
告知義務の期間は、賃貸契約の場合、概ね3年間とされています。ただし、社会的な影響が大きい事件(ニュースになった事件など)の場合は、3年を超えても告知が必要となる場合があります。
(参考:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」)
まとめ:もしもの時は、専門家へご相談を
賃貸物件での自死は、賃借人の遺族も、賃貸人であるオーナー側も、いずれも非常に大きな精神的・経済的負担となります。しかし、適切な知識と冷静な対応があれば、その損害を最小限に抑えることができます。
- まずは警察や管理会社と連携し、冷静に状況を確認する。
- 原状回復が必要な場合は、速やかに特殊清掃業者や工務店に相談する。
- 損害賠償については、契約書を確認し、弁護士などの専門家に相談する。
私たちヨカイエでは、不動産に関するお困りごとについても、ご相談をお受けいたします。もしもの際は、お気軽にご相談ください。








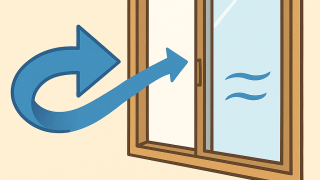









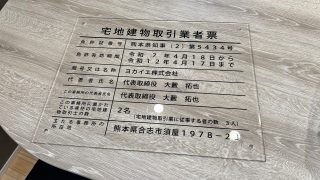



コメント