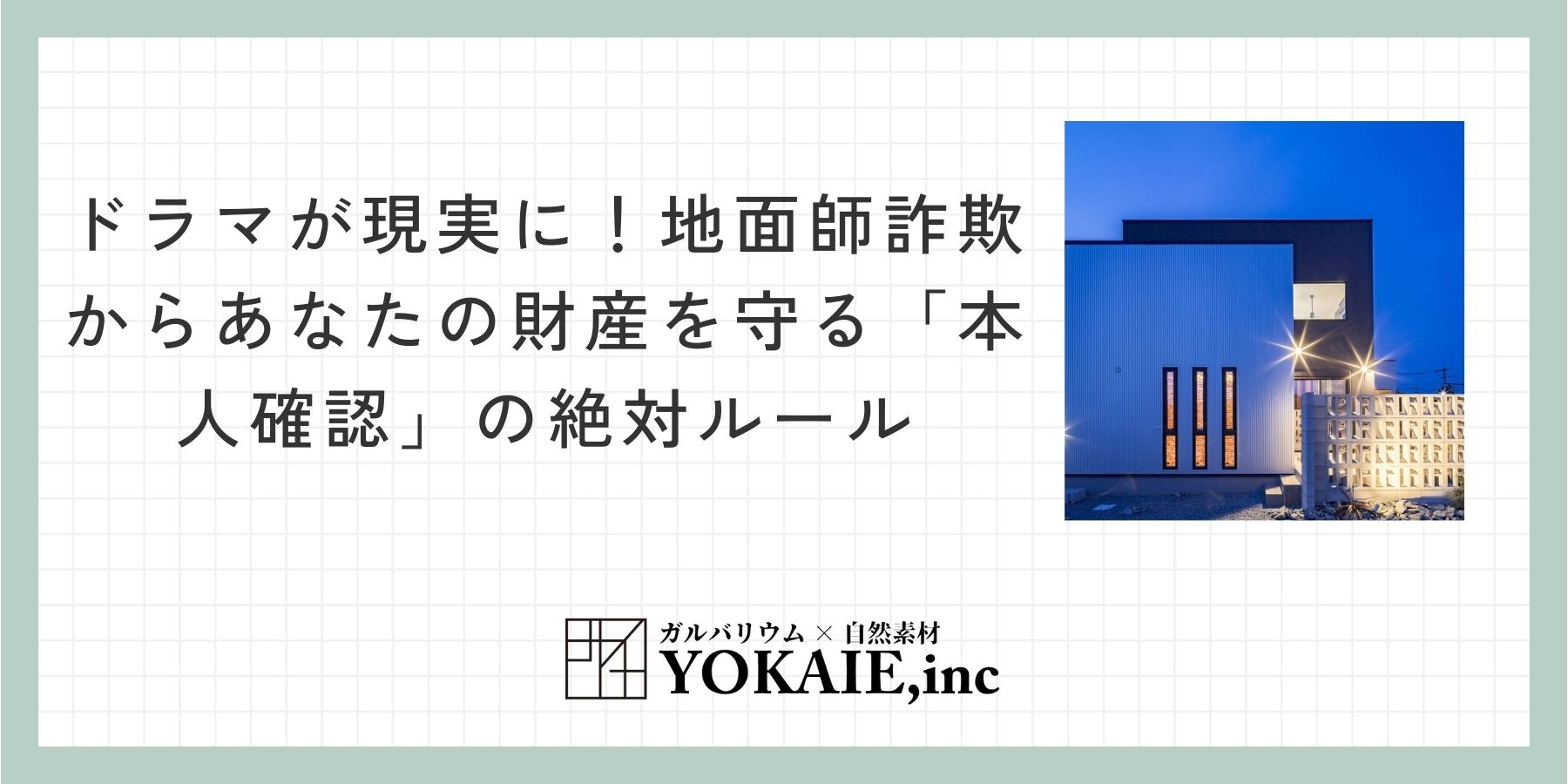
目次
地面師の影が問いかけるもの—不動産取引の根っこを揺るがす「なりすまし」の衝撃
社会的な関心が高まる「地面師」の恐ろしさ
いまさらながら、Netflixドラマ『地面師たち』を見まして。宅地建物取引士として、これは見とかなきゃな…と思いつつ、早1年たちました。当時、地面師たちを見た人たちが、ピエール瀧さんの決め台詞である
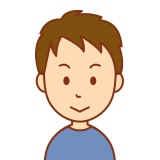
もうええでしょう!!
…を真似してた気持ちが、いまならわかります。
「地面師(じめんし)」とは、不動産の持ち主になりすまして、勝手に土地や建物を売って、代金をだまし取る組織的な詐欺集団のことです。
いやー、土地決済の場に本当にあんなのがいたら、司法書士も帰りたくなると思いますね…。億単位の土地決済にはまだ立ち会ったことはないので、動く額が大きくなるとあれくらいピリピリするのかも。基本的には住宅用の土地決済では、緊張はしますが、淡々と終わる感じです。

本人確認の重要性を再確認。
「地面師たち」での見せ場は、司法書士によるあの緊迫の本人確認シーン。そこで確認されるのは、生年月日や住所だけでなく、干支や最寄りのスーパーはどこか…。はたまた、2枚の写真をならべて、「どちらがあなたの土地の写真ですか?」と尋ねてみたり。実際の地主でなければ答えられないような質問を、司法書士がぶつけてきます。
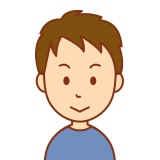
いままでのドラマで、本人確認であそこまで盛り上がる作品があったでしょうか…。
物理的なチェックでは、印鑑証明書と実印の照合はもちろん、ペンライトで免許証のICチップの埋め込みがされているかを確認したり、パスポートにブラックライトをあてて、模様が浮かび上がるか確認したり。そこまで厳しいチェックをしても、まんまと不動産詐欺師に騙されてしまいます。
私たち宅地建物取引士にとって、これはドラマの中の話ではありません。皆さんの大切な財産である不動産の取引の土台を崩しかねない、現実の最大のリスクとして、常に警戒しています。

大事件の教訓:「巨額詐欺」はなぜ防げなかったのか
地面師の恐ろしさを世に知らしめたのが、2017年に起きた積水ハウスの巨額詐欺事件です。
大手不動産会社が、地面師グループに55億5千万円もの大金を支払ってしまったこの事件は、企業の法務部や多くの専門家が関わっていたにもかかわらず、なぜ巧妙な詐欺を防げなかったのかという、大きな教訓を残しました。
問題は、「お金を払った瞬間(=土地決済)」と「正式に名義が変わる手続き(不動産登記)」が終わるまでに時間差があることです。積水ハウスが代金を払った後になって、実はその土地の本当の持ち主が現れ、名義変更が認められなかったという最悪の事態が起こりました。
この事件で再確認されたのは、「決済の瞬間」が、巨額のお金と権利が動く最後の防衛線であるということです。私たち宅建士は、この瞬間に絶対に詐欺を防ぐ責任があるのです。

宅建士の責任:信頼を守るプロとして
不動産取引は「信頼」の上に成り立っています。しかし、地面師の存在は、その信頼が偽造された紙一枚や巧妙な嘘でいとも簡単に崩れることを示しました。
私たち宅建士は、単に書類のチェックリストを埋めるだけでなく、「目の前の人が本当に所有者本人なのか?」という取引の真実性を、命がけで保証する役割を負っています。
地面師の手口の深層—なぜプロでもだまされるのか
詐欺の仕組み:完璧な「なりすまし」
地面師詐欺の基本は、本物の所有者になりきることです。
彼らは、偽造された運転免許証、パスポート、印鑑証明書など、本物そっくりの公的な書類を使って契約を結びます。彼らは文書偽造役、売主になりすます役、交渉役と役割を分担する組織的なプロ集団であり、その偽装があまりに精巧なため、専門家でも見抜くのが非常に難しいのです。
彼らの目的は、自分の物ではない不動産を皆さんに買わせ、その代金をだまし取ることです。

地面師が狙う「危ない物件」3つのタイプ
地面師は、どんな物件でも狙うわけではありません。リスクが低く、すぐにお金に換えられる**「スキのある物件」**を狙います。
| 類型 | 物件の特徴 | 警戒すべき理由(地面師の狙い) |
| A | 抵当権(借金)がついていない物件 | 銀行の厳しいチェック(担保評価など)が入らないため、すぐに取引を終わらせやすく、現金化がしやすい。 |
| B | 長年放置された空き地・空き家 | 本物の所有者との連絡が難しく、近所の目も届きにくい。登記情報も古いままになっていることが多い。 |
| C | 高齢者名義や複雑な所有関係の物件 | 高齢者はだまされやすく、また相続問題などで所有関係が複雑な物件は、管理の隙を突かれやすい。 |
宅建士は、これらの物件の取引では、「最高の警戒レベル」を敷いて臨みます。
登記簿を確認するだけでは不十分な理由
不動産取引で必ず確認するのが「不動産登記簿」です。しかし、地面師詐欺を防ぐ上では、登記簿を見るだけでは決定的な証拠になりません。
なぜなら、登記簿は「誰が権利を持っているか」を示すためのものであって、「今、目の前にいる人が本当にその人本人であること」を証明するためのものではないからです。登記情報には顔写真などの生体情報は載っていません。
地面師は、「登記簿の名前」と「偽造した本人確認書類を持つ目の前の人物」が一致しないという、この制度の限界を巧妙に突いてきます。だからこそ、私たち専門家は、単なる書類チェックではなく、多角的な視点から「本物であるか」を徹底的に確かめる必要があります。
不動産取引の最前線で実践すべき「多重防衛線」
専門家同士の「ダブルチェック」体制
本人確認は、私たち宅建士だけの仕事ではありません。名義変更の手続きを行う司法書士と、契約の背景を詳しく確認する宅建士が、緊密に情報と判断を共有し、二重の防衛線を張るべきだと考えています。
専門家は、公的な書類の細部を確認するだけでなく、「なぜ売るのか?」「いくらで売るのか?」「お金は何に使うのか?」など、売主の売却の本当の意思を深く掘り下げて確認します。地面師は、自分の物ではないため、物件の歴史や生活背景について無知である可能性が高いからです。
現場で察知すべき「危険信号(レッドフラッグ)」
地面師は、取引の確実性よりも「スピード」を重視し、専門家の詳しい調査を嫌がります。以下の兆候(レッドフラッグ)を見つけたら、「危ない」と判断し、取引を一時停止して追加の確認を行います。
- 異常な取引の急ぎ方:
決済を普通ではないほど急いで行おうとしたり、銀行や不動産会社ではない不自然な場所で現金の受け渡しを強行しようとしたりする。- 物件の知識不足:
売主が、物件の古い歴史や細かい管理状況、近所の人との関係についてあいまいな答えしかできない。- 公的書類の不自然さ:
偽造防止の技術(フォントのずれ、印刷の精度など)に違和感がある。また、印鑑証明書などの発行日が古すぎる、あるいは発行機関が遠すぎるなど、不自然な点がある。- 高齢者名義での代理人の不自然さ:
代理人が出てきた場合、その代理権の範囲や、所有者本人の判断能力が今も適切かを、第三者や専門家(弁護士・司法書士)を通して厳しく確認します。
地域の情報と実地調査の活用
リスクの高い空き地や放置物件では、書類だけでなく、アナログな情報収集が有効です。
「近所の人や地域住民に話を聞いてみる」ことで、本物の所有者が長年不在だったことや、売主を名乗る人物の出入りがあったかどうかなど、なりすましを防ぐための状況証拠が見つかることがあります。プロは「効率」よりも「確実」を優先し、常に「もしかしたら?」という疑いの目を持って現場を検証します。
デジタル時代の防衛戦略—eKYCと電子署名がもたらす革新
不動産取引のデジタル化

2022年5月の宅建業法の改正により、不動産取引のデジタル化が大きく進みました。
これまで紙でしかダメだった重要事項説明書や売買契約書などの大切な書類が、電子データで交わせるようになったのです。これにより、改ざんを防ぐための厳格なシステム利用(タイムスタンプなど)が義務付けられ、紙の書類よりも書類の真実性が守られやすくなっています。
eKYCとマイナンバーカードの活用
本人確認の未来は、「偽造しにくいデジタルな身元証明」に移行しています。
- eKYC(電子的本人確認): スマホで手軽に本人確認を済ませられる技術で、厳格な認証プロセスを実現します。
- 公的個人認証サービス(JPKI): マイナンバーカードを使った認証サービスです。公的なIDと個人の顔画像などの生体情報を強力に結びつけられるため、紙のIDを偽造するという地面師の得意な手口を過去のものにする可能性を秘めています。
登記手続きのパスワード「登記識別情報」
名義変更の登記手続きでは、所有者固有の12桁のパスワードである「登記識別情報」が非常に重要です。
これは権利移転の真実性を示す「鍵」であり、私たち宅建士は、この重要な情報が決済の瞬間に司法書士によって厳格に扱われているかを、責任をもって確認する義務があります。
第4章:プロフェッショナルによるリスクマネジメント実践チェックリスト
リスクな取引に臨む際、「三層防御」という考え方で本人確認を行います。
- 意思の確認:
売主の「売却の意思」は本物か?- 関係性の確認:
権利の「正当な関係性」があるか?- 技術的な正当性の確認:
書類やデジタル情報の「真正性」は守られているか?
以下の表は、地面師が狙いやすい物件に対する、私たちの具体的なチェックポイントです。
| リスク特性(地面師の標的) | 確認 I (意思の確認) | 確認 II (関係性の確認) | 確認 III (技術的な正当性の確認) |
| 抵当権がついていない物件 | なぜ急ぐのか、売却代金の使い道を深く聞く。 | 権利関係や税金の支払い履歴をチェック。 | マイナンバーカードによる公的認証(JPKI)を推奨し、厳しくIDの真偽を確かめる。 |
| 長年放置された空き地・空き家 | 物件の取得経緯や細かい管理状況を質問し、知識に矛盾がないか検証。 | 近所の人に聞き込みをし、所有者との関わりを確かめる。 | 登記識別情報が正しく管理されているか、司法書士と連携して確認。 |
| 高齢者名義、複雑な相続物件 | 代理人がいる場合、委任状の作成経緯や、売主本人の判断能力を厳しく確認。 | 弁護士や司法書士も交え、複雑な権利関係を解消。 | 最新の公的書類(印鑑証明書など)を厳しく確認し、必要に応じて取り直しを求める。 |
結論:「信頼」を担保するプロフェッショナルとしての使命
過去の巨額詐欺事件が教えてくれたのは、不動産取引の安全は、書類の見た目や手続きの完了ではなく、私たち専門家一人ひとりの「疑う心」と「新しい技術への対応力」にかかっているということです。
私たち宅建士は、皆さんの大切な不動産という財産を守る最後の砦として、以下の3点を常に実行し続けます。
- 「疑う心(懐疑心)」を持ち続ける:
取引を早く終わらせたいという誘惑に負けず、売主本人の「同一性」と「売る意思」を常に疑い、多角的に検証する姿勢を崩しません。- 連携を強める:
司法書士、弁護士、地域住民など、外部の専門家や情報源と密に連携し、一人で判断せず、多重チェックで安全性を高めます。- 技術を使いこなす:
電子契約やeKYC、JPKIなど、デジタル技術による高度な防衛策を積極的に導入し、紙の偽造対策だけでなく、未来のデジタル詐欺にも備えます。
私たち宅建士は、この専門家としての使命感を胸に、皆さんの取引の「信頼」を担保し、安全な不動産市場を守り続けます。
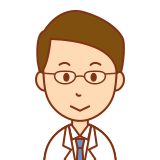
ヨカイエは熊本の工務店です。
不動産業の免許を持っておりますので、家づくりのための土地選びでは、ぜひ当社にお任せください。建築関連法規に精通している当社であれば、おうちづくりにとってベストな土地選びにお役に立てると思います。












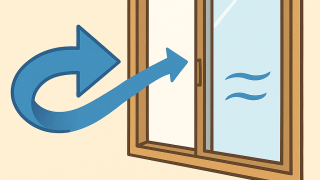



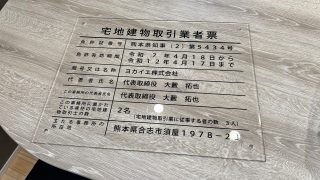

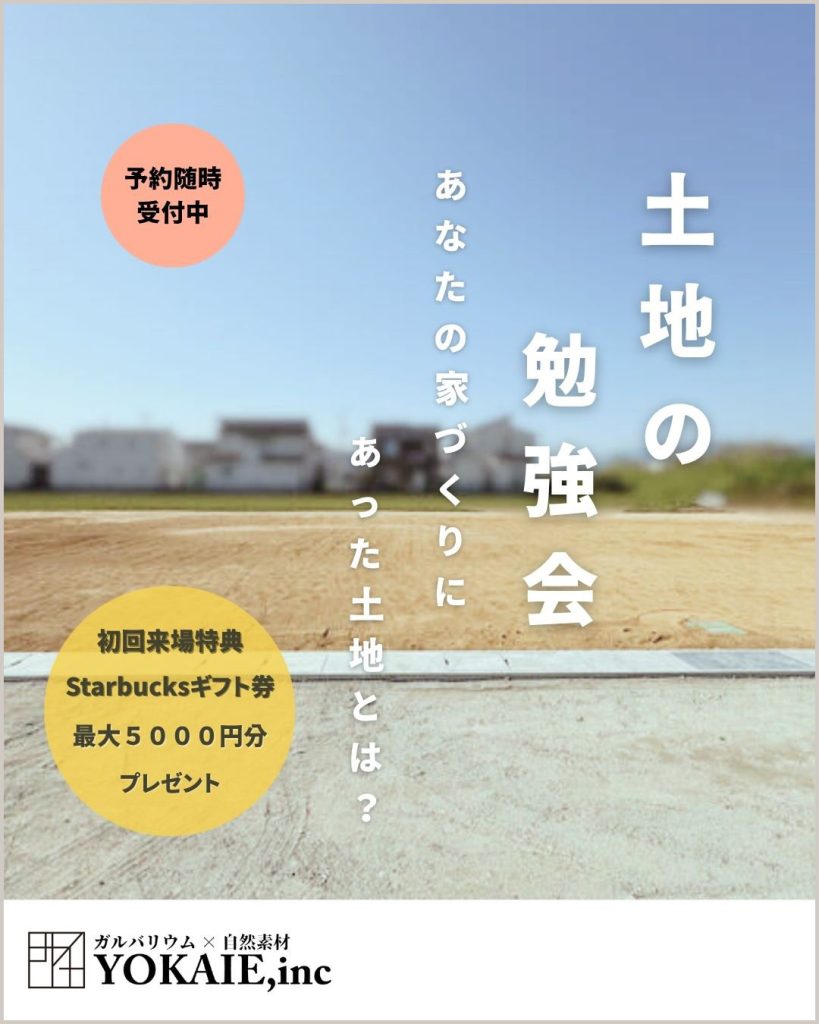


コメント