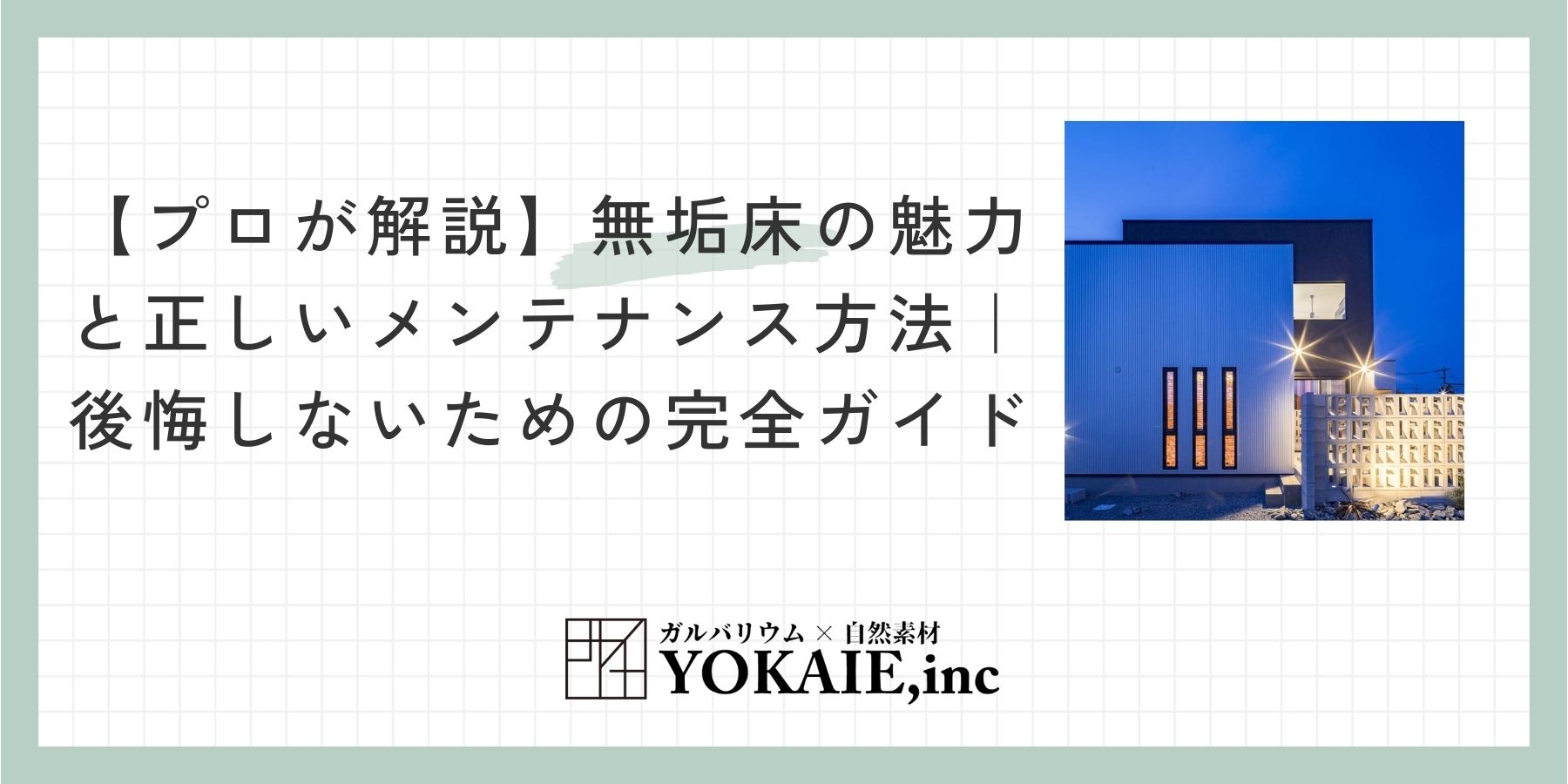
家づくりにあたって、健康的であたたかみのある無垢床は、あこがれるもの。しかし、いざ導入を考えると、いろんな疑問が湧いてくると思います。

無垢床は、維持メンテナンスはたいへんじゃないの?
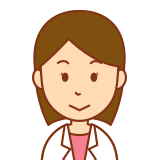
無垢床が割れることがあるって、本当なの?
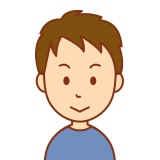
へこんだときは、自分で修理できるものなの?
今回は、メンテナンスも含めて、無垢床を徹底解説していきますので、最後までご覧ください!

そもそも、無垢床ってどんなもの?
無垢床とは、一本の木から切り出した単一素材の木材をそのまま床材に使用したものです。
複数の素材を貼り合わせてつくられる突板フローリングとは異なり、素材そのものが持つ風合いや質感をそのまま感じられるのが最大の特徴です。手で触れたときのぬくもりや、足元から伝わる自然な温かさは、突板フローリングにはない魅力です。
突板フローリング
天然木材を薄くスライスしたものを、合板に貼ったもの。本物の木材といえるのは、フローリングの表面ほんの0.3mm〜0.5mmだけで、残りの大部分は、パルプを圧縮したMDF材や、合板となります。
無垢床(15mm)であれば、厚み15mmすべてが天然の木材になりますので、汚れたときにほんのわずかに表面を削り取って、新品同様に再生することも可能なわけです。
また、時間とともに色合いや質感が変化し、経年変化を楽しめるのも無垢床ならではの特徴といえるでしょう。先日、建ててから20年経過した無垢床のお家を拝見させていただく機会がありましたが、オーナー様のメンテナンスが行き届いていたこともあり、無垢床ならではの深い味わいを感じることができました。
無垢床を採用するメリット
無垢床のメリットは、自然素材ならではの温かみと癒し効果です。
木の香りが漂い、室内にいるだけで森の中にいるようなリラックスした気分を味わえます。また、断熱性・調湿性に優れており、夏はさらりと涼しく、冬はほんのり温かい感触を保ってくれます。
また、接着剤で重ね合わせた突板フローリングとは異なり、シックハウス症候群の原因物質「VOC」(揮発性有機化合物)を出さないという点も、ちいさなお子さまがいらっしゃるご家庭では大事なメリットになると思います。お子さまが幼いうちは、大人と違って化学物質への感受性が高いため、有害物質の影響を受けやすくなります。
【参考】自然素材住宅にするべきじゃないことも?自然素材のメリット・デメリット
さらに、万が一傷がついても、表面を削ることで再生可能という点も、長期的に見たときに大きな利点となります。
シックハウス症候群とは?
シックハウス症候群とは、住宅や建物の中にいると頭痛やめまい、目や喉の痛み、湿疹、倦怠感などの体調不良が出る症状の総称です。
これは特定の病気というよりも、建材や家具に含まれる化学物質、または換気不足などが原因で起こる健康被害です。
主な原因
ホルムアルデヒドなどの化学物質(合板や接着剤に含まれる)
新築時・リフォーム時の内装材(クロスや塗料)
家具やカーペットなどからの揮発性有機化合物(VOC)
換気不足による空気の滞留

無垢床のデメリット
一方で、無垢床にはデメリットも存在します。
まず、湿度によって木が膨張・収縮するため、施工時には木の動きを考慮した設計が必要です。膨張・収縮が起こらないようにするためには、まずしっかりと木材の含水率を下げた、きちんと乾燥させた確かな材料を選ぶ必要があるでしょう。
平衡含水率とは?
大気の湿度と、木材の水分量が均衡した状態の含水率を平衡含水率といいますが、屋外であれば15%~20%と言われています。つまり、屋外であれば含水率15%あれば収縮・膨張が起こらないことになります。
しかし、現代の高気密化された屋内では、暖房器具が使われたりする季節では平衡含水率は10%程度になると思われます。無垢床を選ばれる際には、含水率がどれくらいの材料なのかは、チェックすべきでしょう。
また、傷がつきやすく、特に重いものを落としたり、家具を引きずると跡が残ってしまいます。さらに、水分に弱く、濡れたまま放置するとシミや反りの原因になりますので、コーヒー等をこぼした際にはすぐに拭き取ることが肝心です。
美しさを保つには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

突板フローリングとの違い
突板フローリングは、薄くスライスした天然木を合板の表面に貼り付けたものです。
見た目には無垢材と似ていますが、表面の厚さが非常に薄いため、再研磨や補修はほとんどできません。コストや施工性では突板フローリングに優位性がありますが、質感や経年変化を楽しめるという点では無垢床に軍配が上がります。
自然素材にこだわる人にとっては、やはり無垢材の存在感は格別です。
樹種による、性質の違い(広葉樹、針葉樹の違い)
無垢床に使われる木材は、主に広葉樹と針葉樹に分けられます。
広葉樹(ナラ、ウォールナット、チェリーなど)は硬くて耐久性があり、重厚感のある雰囲気を演出できます。一方、針葉樹(スギ、ヒノキ、パインなど)は柔らかく、素足にやさしい感触が特徴です。使う部屋の用途やライフスタイルに応じて、適切な樹種を選ぶことが、無垢床を長く楽しむコツとなります。
無垢床のメンテナンスの重要性
無垢床の弱点(傷がつきやすい、水に弱い)
無垢床は非常にデリケートな素材です。特に傷や水に弱いという特性を持っています。
小さなお子様がいるご家庭やペットを飼っている家庭では、どうしても傷がつきやすくなります。また、飲み物をこぼしたり、濡れた傘をそのまま置いてしまったりすると、水分が木材に染み込み、膨張や変色の原因になります。
このような弱点をしっかり理解し、日頃から丁寧な扱いを心がけることが求められます。
表面塗装である程度の耐久性は維持されるが…
無垢床には出荷時に表面塗装が施されているものが多く、これによりある程度の耐久性が確保されています。
オイル仕上げやウレタン塗装など、仕上げの方法によって耐水性や手入れのしやすさが変わってきます。しかし、どの仕上げであっても、年月とともに塗膜は劣化します。
そのため、塗装に頼りきりにならず、定期的な再塗装や日常的なケアが欠かせません。
無垢床のメンテナンスはたいへん?
「無垢床は手入れが大変」というイメージを持たれがちですが、正しい方法と頻度を理解していれば、決して手間ばかりではありません。むしろ、自分の手で木の状態を確認し、必要に応じてオイルを塗ったり、汚れを拭き取ったりする行為そのものが、暮らしを豊かにする一部になります。
無垢床とのつきあいは、家具や家電のように使い捨てるのではなく、育てていく感覚に近いものです。
メンテナンスしなかったときの、10年後、20年後の状態
もし、無垢床のメンテナンスを怠るとどうなるのでしょうか?
日々の使用による汚れや傷が積み重なり、数年で表面がくすみ、色ムラやシミが目立つようになります。10年、20年と放置すれば、床材そのものが反りや割れを起こし、張り替えが必要になることもあります。
こまめな手入れをするか否かで、同じ素材でもまったく異なる経年変化を遂げるのが、無垢床の特徴でもあるのです。
やりがちなNGメンテナンス
無垢床の手入れには、避けるべきNG行動もあります。たとえば、強い洗剤を使ってゴシゴシこすったり、水拭きを頻繁に行うと、木の表面を傷めてしまいます。
また、スチームクリーナーの使用もNGです。高温の蒸気が木材の奥深くまで入り込み、反りや割れを引き起こすリスクがあります。正しいメンテナンス方法を知ることが、美しさを保つ第一歩です。
無垢床は無塗装はおすすめしません
無塗装だと汚れが取りにくくなります。
無垢床の中には、あえて塗装を施さずに素材そのままを楽しむ「無塗装タイプ」も存在します。
しかし、無塗装のままだと、汚れが木の内部に浸透しやすく、シミや変色が取りにくくなります。また、直射日光があたると日焼けが進行していきます。手入れのしやすさや、衛生面を考えると、やはり最低限の表面保護は必要です。
無垢材の良さを活かしながら、日常使いの中で実用性を持たせるには、適切な塗装が欠かせません。
無垢床で使用される塗装の種類
無垢床に使用される塗装には主に「オイル仕上げ」「ウレタン塗装」「自然塗料」などがあります。
オイル仕上げは木材に浸透し、呼吸を妨げない自然な質感が魅力です。一方、ウレタン塗装は表面に膜をつくり、水や汚れに強くなります。自然塗料は環境や健康への配慮がされており、小さなお子様やペットがいる家庭におすすめです。目的に応じた塗装選びが、快適な無垢床ライフを支えます。

劣化対策のため、どのようなメンテナンス方法をすればよいか
木の質感を損なわないワックスなどでコーティングをする
メンテナンスには、木の質感を損なわない専用のワックスやオイルを使用することが重要です。
市販のフローリング用ワックスの中には無垢材に適さないものもあるため、必ず対応素材を確認しましょう。特にオイルフィニッシュの床には、植物性オイルを使ったメンテナンスオイルが効果的です。
当社では、リンレイの床ワックスを使用しますが、こちらは天然由来成分(米ぬか、蜜蝋など)だけを使ったワックスという点で、当社の自然素材住宅のコンセプトとも合致しており、まだコストパフォーマンスもかなり高い製品となっております。幼いお子様や、インコや犬猫などペットを飼っていらっしゃる方には特にオススメです。
塗布後はしっかり乾燥させることで、木の内部に浸透し、耐久性を高めてくれます。

メンテナンス期間は?
メンテナンスの頻度は使用状況や塗装の種類によって異なりますが、一般的には年に1〜2回のオイル塗布が推奨されています。また、日常の掃除としては、乾拭きや柔らかいモップでの掃き掃除が基本です。無垢床は水を吸うため、水拭きは、よく水気をきってから、あまり高頻度には行わないようにしましょう。
こまめな掃除と定期的なオイルケアが、美しい床を長持ちさせる秘訣です。
傷、シミができた場合の対策
小さな傷(ささくれ等)であれば、240番くらいの目の細かいサンドペーパーで軽く磨いた後、木部用塗装オイルを塗布することで目立たなくなります。範囲が広い場合には、電動サンダーなどを使って研磨する必要がでてきます。
軽いへこみなどは、濡れ布巾の上からアイロンをあてることで、もとに戻すことができます。木の膨潤性という性質を活かしたものですね。
補修のプロに依頼するのも、1つの手。
深い傷や広範囲のシミは、専門のリペア業者に相談するのもひとつの手です。当社で依頼している熊本市のリペア業者(株式会社Sreef様)は作業時間単位での請求になっていますので、あらかじめ補修箇所をマスキングテープでマーキングして、最低料金となる90分で依頼して、できるかぎり直してもらったりしています。
正直、補修された箇所は凹みなどは綺麗さっぱりわからなくなるので、目立つ傷などはプロに依頼することを断然おすすめいたします!
90分作業 ¥10,000〜¥15,000 3時間作業 ¥15,000〜¥25,000 7時間作業 ¥25,000〜¥35,000 延長 30分につき¥2,000 材料費 材料費は作業内容により頂く場合がございます。 移動費 20キロ圏内は移動費はかかりません。20キロ以降は都度お見積り致します。お問合せ下さい。
早期に対処すればするほど、無垢床の美しさを保ちやすくなります。放置せず、見つけたらすぐに手を入れる習慣をつけましょう。
節が抜けてしまったときの対策
無垢材には、木の個性ともいえる「節」がありますが、まれにこの節が抜け落ちてしまうことがあります。
その場合は、木製のパテや補修用の埋め木を使用して補修します。専門業者に依頼すれば、違和感のない仕上がりにしてくれるので、無理に自分で直そうとせず、プロに頼るのもおすすめです。
日焼け対策
無垢床は紫外線によって色が変わる性質があります。これを「日焼け」と呼びますが、必ずしも悪い変化ではなく、経年美として楽しむ人も多いです。ただし、家具を長期間同じ場所に置くと、その部分だけ日焼けしないため、色ムラが目立つこともあります。
定期的に家具の配置を変えたり、UVカットのカーテンを使ったりすることで、均一な日焼けを促すことができます。
まとめ
無垢床は、自然素材ならではの温かみや癒し効果を備えた、住まいに豊かな表情をもたらしてくれる床材です。
しかし、その魅力を最大限に引き出し、長く美しく使い続けるためには、適切なメンテナンスが不可欠です。傷や汚れ、水分への注意を怠らず、正しい方法で日々のケアを行うことで、無垢床は年月を経るごとに味わいを深めていきます。手をかけた分だけ応えてくれる、それが無垢床の大きな魅力です。
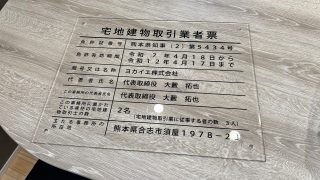








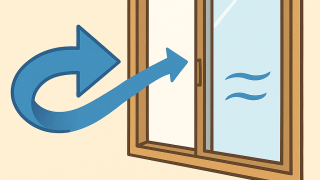











コメント